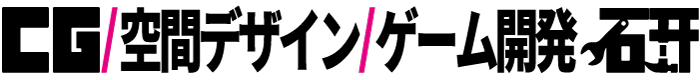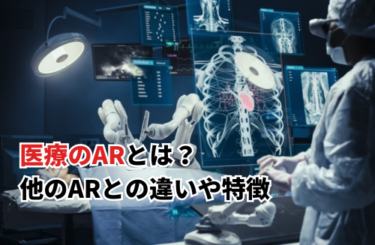ARとVR技術の実用化は目まぐるしいスピードで進んでおり、日常生活のおける様々なシーンに導入されています。ARやVRの動画は身近な技術として広まっていますが、その違いについてはあまり認知されていません。
今回はARとVRにそれぞれの特徴や違いを掘り下げていきましょう。
ARの概要と特徴

まずはARとは何かや特徴について理解しましょう。
ARの基礎知識
ARは「Augmented Reality」の頭文字を取ったもので、日本語では「拡張現実」と訳されることが多いです。歴史的に見ると劇作家のライマン・フランク・ボームが1901年に提唱したアイデアが、ARの源流とされています。1990年にはVRから派生する形でARという言葉が誕生しました。
ARの名付け親は、当時ボーイング社の技術者であったトム・コーデルとされています。
ARは現実世界の映像に視覚的なデジタル情報を加えることで、あたかも現実が拡張したかのように見せる技術のことです。
ARは大きく分けて3種類
ARには下記の3種類があり、それぞれで映像合成のトリガーとなるものが異なります。
- ロケーションベース
- マーカー型
- マーカーレス型
ロケーションベースのAR
ロケーションベースのARは端末の位置情報をトリガーにしてARを起動するタイプです。
主にGPSシステムを利用するため、GPS型と呼ばれることもあるので留意しておきましょう。
比較的サービスを開発しやすいという点がメリットですが、位置情報の正確さが品質を大きく左右します。緯度・軽度の位置情報以外にも、端末の傾き・向いている方向・磁気センサー・加速度センサーなどのデータを活用して、位置情報の精度を高めることが可能です。
マーカー型のAR
マーカー型とマーカーレス型のARはビジョンベースと呼ばれることもあり、ビジュアルデータをトリガーにしてARを起動させる技術です。
マーカー型のARでは画像やイラストといったコンテンツを使用し、読み込んだデータが事前に登録してある特徴に一致する場合にARが起動します。このARでは読み取り位置にデジタル情報を付加するため、精度の高いコンテンツを開発しやすい点がメリットです。
一方、画像やイラストなどを端末で読み取る必要があるため、光源や端末性能によっては読み取りが安定しないことがネックといえるでしょう。
ARを起動させるためのマーカーを事前に設置しておく必要もあります。
マーカーレス型のAR
マーカーレス型のARは端末で撮影している風景や立体物をトリガーにしてARを起動させる方法で、
- 空間認識型
- 物体認識型
の2パターンに分類されます。特定の場所に限定されないため幅広いシーンで活用できる点がこのARのメリットですが、リアルタイムでの空間計算が必要となるため処理が重くなるというデメリットもあるので留意しておきましょう。ARの精度を確保するためには高い技術力が要求されます。
ARの活用事例
- 携帯用ゲーム「ポケモンGO」
- 自宅に家具を試し置きできる「IKEA Place」
- 端末で読み取ることで教材のデータを立体化
ポケモンGO
ARの活用事例として有名なものには、ナイアンティック・ラボが開発した携帯用ゲーム「ポケモンGO」が挙げられます。同作ではGPS型とマーカーレス型のAR技術が採用されており、街中で撮影した現実空間にポケモンが浮かび上がるという仕組みです。原作の人気とARサービスの斬新さが相まったヒット作として、多くのユーザーから支持を集めました。
IKEA Place
大手家具販売店のIKEAでは、自社アプリとして自宅に家具を試し置きできる「IKEA Place」をリリースしています。自宅内で任意の場所を撮影すると、マーカーレス型のAR技術によって購入を検討している家具が浮かび上がってサイズ感や色味を確認できるサービスです。
教材のデータ
東京書籍では教科書にARマーカーを仕込み、端末で読み取ることで教材のデータを立体化することに成功しています。立方体や多面体の図形・歴史的な資料・理科系の模型など、ARで立体にすることで学習効果や効率の向上が期待できるものは少なくありません。
ARについてはこちらの記事でも詳しく紹介しています。
VRの概要と特徴

ARに続いて、VRとは何かや特徴について見て行きましょう。
VRの基礎知識
VRは「Virtual Reality」の略称で、日本語に訳すと「仮想現実」です。
1935年にアメリカのSF作家であるスタンリイ・G・ワインボウムが発表した『Pygmalion’s Spectacles』の中で描かれたゴーグルシステムが、VRの原型になったとされています。
VRという言葉そのものが誕生したのは1989年のことで、アメリカの計算機科学者ジャロン・ラニアーによって名付けられました。VRではコンピューターによって作られた世界へユーザーが没入することで、現実世界とは切り離された臨場感のある空間を体験できます。
VRの仕組み
VRでは仮想空間が立体的に広がる点が大きな特徴ですが、これは人間の目における「両眼視差」という現象を利用したものです。通常、人間の目は左右それぞれで微妙にズレた景色を捉えています。このズレ(両眼視差)を脳が修正することで、物体の大きさや距離感を正確に把握し、正常な立体映像として認識できるようになるのです。
VRデバイスは左右の目に映る映像をわざとズレたものにすることで、脳に修正させ立体的に感じるようにしています。視力の状態は人によって様々なので、VRデバイスの多くはピント調節機能を備えているのも特徴です。
VRの活用事例
- 家庭用ゲーム機の「PlayStation VR」
- 音楽ライブをVRコンテンツ化
- VRで仮想空間を散策する擬似的な旅行体験
- 手術の実施前にVRでシミュレーション
- VRシミュレーションによるリスク回避
PlayStation VR
VRの活用事例はエンタメ業界で多く知られています。例えばソニー社では家庭用ゲーム機の「PlayStation VR」がリリースされており、自宅に居ながら手軽にVRによる仮想空間を楽しめるようになりました。
音楽ライブ
新型コロナウイルスの影響によって非接触型サービスの開発が進んだことも、VRの普及に追い風となっています。例えば音楽ライブをVRコンテンツ化することで、視聴者が自宅に居ながら様々な角度からアーティストの姿を見られるようになりました。
旅行体験
影響が甚大だった旅行業界においても、VRコンテンツの仮想空間を散策して、擬似的な旅行体験を提供するプランが話題となったのです。
シミュレーション
VRで投影される仮想空間は現実世界の法則に基づいた設定も可能であり、リスクやコストの試算・削減にも活用されています。医療業界では手術の実施前にVRでシミュレーションを行い、予期せぬトラブル防止と成功率向上に役立てる取り組みが見られるようになりました。機材追加やプロセス変更に大きなコストが伴う製造業においても、施策実施前のVRシミュレーションがリスク回避に大きく貢献しています。
VRについてもっと詳しく知りたい方にはこちらの記事がおすすめです。
ARとVRの違いとは
続いてARとVRの違いについて確認しましょう。
| AR | VR | |
| メインとなる世界 |
|
|
| 必要なデバイス |
|
|
体験のメインとなる世界
ARとVRではユーザー視点でメインとなる世界観が異なります。
ARの場合はあくまでユーザーの視点は現実世界に留まっており、視覚的なデジタル情報がデバイスから飛び出してくるイメージです。
これに対してVRではデバイスを通じて仮想世界に入り込むため、ユーザーの視点は現実世界には残りません。ARは現実世界、VRでは仮想世界が体験のメインとなる世界なのです。
必要なデバイス
ARもVRも原則として投影に対応したデバイスが必要になりますが、その種類に大きな違いがあるので留意しておきましょう。ARはスマホやタブレットのようなモバイルデバイスがメインであり、場合によってはARグラスと呼ばれる専用機器を用いることもあります。
VRでは視界を覆って仮想空間を投影するため、基本的にはVRゴーグル・グラス・ヘッドマウントディスプレイ(HMD)といったVR専用のウェアラブルデバイスが必要です。
また、パソコンやゲーム機本体のようにVRの仮想空間を生成するためのデバイスも用意します。
ARとVRの違いについてはこちらの記事もご覧ください。
ARのことが分かる動画
ARについて分かる動画を3つ紹介します。
キノコード / プログラミング学習チャンネル
こちらはARの特長を3分程度にまとめたビギナー向けの分かりやすい動画です。
図解付きなのでARの予備知識がなくてもイメージしやすくなっています。
ディスカバリーチャンネル
登録者数182万人(2023年10月13日時点)を誇る人気コンテンツ「ディスカバリーチャンネル」によるARおよびVRの解説です。歴史の流れに沿った丁寧な説明が施されており、ARやVRが一般的に広まるまでのプレセスを分かりやすく追いかけられます。
モシモノセカイ
ARの将来性について知りたい場合におすすめの解説動画です。
ARの実際の活用シーンを引き合いに出しながら今後の可能性を論じているため、現実味のある未来像がイメージできます。
VRのことが分かる動画
VRについて紹介している動画を3つ紹介します。
アリマックスのVR / Arimax VR
VRの概要を丁寧に解説した約15分の動画です。
実例のVR映像を交えながら話を進めてくれるので「VRにできること」を分かりやすく理解できます。
360度VRラボ / 株式会社ブリッヂ
VRの活用方法をビジネス的な観点から解説しています。
既に実用化されたVRのサービスを軸にしているため、VRのアイデア出しの参考資料として有用性の高い動画です。
CBCニュース【CBCテレビ公式】
2022年5月に放映された番組の一部を公式チャンネルで公開したものです。
VRと親和性の高いメタバースについて深く掘り下げた内容で、実際のVR利用者を取材したリアリティのある内容となっています。
AR・VRへの理解を深めて有効活用しよう
ARとVRは共に成長分野といわれており、今後の展開が期待されています。
既に実用化されているARやVRのサービスも多いので、その利便性や独特の世界観を体験することは難しくありません。ARとVRはプライベートで楽しむも良し、ビジネスに活用するも良し、ARとVRの違いについて理解を深めて生活に役立ててみてください。